新・気まぐれ読書日記 (52) 石山文也 琥珀の夢(その1)
明治12年の年が明けてほどなく“商いの都”大阪、道修町に近い釣鐘町の一角でひとりの男児が産声を上げた。江戸期から両替商を営む三代目鳥井忠兵衛、こまの第4子、次男で信治郎と名付けられた。道修町は江戸時代から薬種問屋が集まり「薬の町」として知られる。現在では田辺三菱のほか、武田薬品工業、塩野義製薬など日本を代表する製薬メーカーが本社を構えているものの「どしょうまち」と正確に読めた20代は10%を割り込んだことがつい最近もニュースになった<なにわ難読地名>のひとつである。
『琥珀の夢 小説 鳥井信治郎』(伊集院 静、集英社刊)は、その次男坊を主人公にした小説である。13歳で道修町の薬種問屋の丁稚となり、薬種以外の合成葡萄酒の製造などを学び、20歳で鳥井商店を興すと洋酒造りと販売にまい進していく。研究を重ね「赤玉ポートワイン」を発売、さまざまな新事業、新製品開発にチャレンジするなかで周囲の大反対を押し切って日本初の国産ウイスキーの製造事業に乗り出した。鳥井商店は寿屋、サントリーと社名は変わるが、戦争などさまざまな苦難を乗り越えて世界有数の企業となったそのバックボーンには信治郎の「生き方」があった。
いわゆる企業小説や経済小説とは縁がなかった著者が日本経済新聞からの執筆依頼を引き受けたのは「信治郎の生涯を書くことは日本人の仕事に対する考え方、ひいては日本人とは何かということにつながると思ったからだ」と新聞インタビューに答えている。
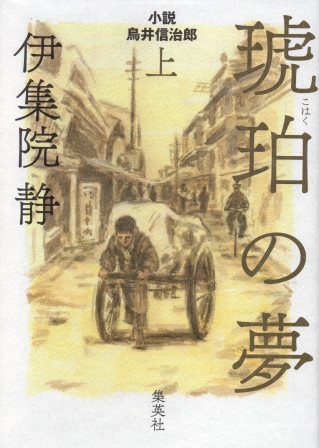
伊集院 静 著『琥珀の夢 上』集英社刊
信治郎は三歳の頃、死地をさまようほどの重い病にかかった。このとき、信心深かった母のこまは御百度参り重ねたが、治ってからは決して体躯の大きくなかった息子の足腰を鍛えようと手を引いて天満天神や四天王寺へ連れていった。人が集まるこうした場所には物乞いがずらりと並んでいた。天神さんへ向う天神橋も別名“物乞い橋”と呼ばれ、橋が近づくとこまは信治郎に小銭をくれるが「お銭(ぜぜ)あげたかて振り向いたらあかんで。振り向いたらあかんよってにな」と鬼のような顔で言い聞かせた。少しでもキョロキョロしようものなら恐ろしく強い力で手を引っ張った。普段やさしい母が、どうして物乞いに施しをした後、彼らを振り向いて見てはならないときつい口調で命じたのかはずっと疑問だったが後年、ある意味の「陰徳」ではなかったかと思い至ったという。
信治郎が丁稚奉公に入った小西儀助商店は、倒産寸前まで追い込まれた店を彦根の薬屋で修行を積んだ奉公人だった店主が当時大阪にはなかった薬を刻む技術で借財を完済して身代をつないだ。研究熱心で知られ、店の仕事が終わった後の夜鍋もいとわなかった。信治郎は他の丁稚仲間が敬遠するこの手伝いを進んでつとめるうちさまざまな薬品の調合や活用知識を蓄えていく。手がけたのは合成葡萄酒、ブランデー、ベルモト酒はいまのブランデーである。失敗を重ねながらも実験の手控えだけでなく頭の中に膨大な知識が詰め込まれていった。近江商人に伝わる商売のやり方である<売り手良し><買い手良し><世間良し>の「三方良し」の精神も教わった。「商い言うもんは、山を見つけたら誰より先に登るこっちゃ。人がでけんことをやるのが商いの大事や」ということも叩き込まれた。
鳥井商店を開業したのは明治32年2月1日。京町堀と阿波掘にはさまれた細長い土地の間口2間の狭い店だった。商売の中心地の船場とは川を隔てた西へ延びる一画で、淀川から船で入る葡萄酒樽などは店の真裏から直接荷揚げできた。商いの中心となる葡萄酒の製造販売には欠かせない製瓶商が近くにあり、甘味を出すのに必要な砂糖商もある。何より大切な得意先の外国人居留地が橋を渡った中州にあったから、注文を受けるにも納品にも最良の場所だった。自前の「向獅子」ブランドの葡萄酒は東京、大阪だけでなく名古屋、九州圏でも国産のシェアトップの東京の「蜂印」には歯が立たない。経営の基盤となったのは缶詰、洋酒、炭酸水などで、店頭に置いてもらえたとしてもお付き合い程度でしかなかった。しかも日清戦争で軍への大口納入話を仲介した男に代金を踏み倒されて店が潰れかけるなど苦労が続いた。
明治39年9月1日に信治郎は屋号を寿屋洋酒店に変更した。新しい門出に際し葡萄酒のラベルもあざやかな金粉を加えた印刷に仕上げ、店内に棚を設けて並べ、問屋にも同じように陳列してもらった。さらに4色の色彩絵具で商品名を浮き彫りにした檜造の宣伝看板を各問屋や商店へ自らが木工店の職人と出向いて掲げてもらうと手代にも看板のお守代として祝儀袋を忘れなかった。得意先を回るのに購入したのは当時、百円、現在なら50万円以上もした輸入品の「ピアス号」で、昼間の船場界隈を「すまへーん、すまへーん、気い付けておくれやす、すまへーん」と猛スピードで走り回った。
購入先の五代自転車店の丁稚だったのがのちの松下幸之助で幸吉どんと呼ばれていた。修理したピアス号を届けるシーン。
棚の葡萄酒を珍しそうに眺める幸吉少年に信治郎は
「ところで今、何を見てたんや」
「す、すんまへん。こ、この棚の葡萄酒があんまりきれいなんで、つい見惚れてもうて。ほんまにすんまへん」
「何も謝ることはあらへん。坊の目にこの葡萄酒が綺麗に見えたか。そら、嬉しいこっちゃ」
「坊は故郷(くに)はどこや?」
「和歌山の海草だす」
「そうか、坊は紀州か。紀州は昔からええ商いがでける商人を出しとる土地や。坊も気張るんやで」
嬉しそうに信治郎を見返した目に強い光があったのに気付くとさらに続ける。
「坊には見どころがある。この棚の、この葡萄酒が綺麗やと思えることが商いの肝心のひとつや。商いはどんなもんを売ろうと、それをお客はんが手に取ってみたい、使うてみたい、この葡萄酒ならいっぺん飲んでみたいと思うてくれはらなあかん。それにはどこより美味いもんやないとあかんのや。ええもんをこしらえることが肝心や。ええもんをこしらえるためには人の何十倍も気張らんとあかんのや。そうやってでけた品物には底力があるんや。わかるか。品物も人も底力や。坊、気張るんやで・・・」
信治郎は丁稚の頭をやさしく撫でた。
この少年がのちに“経営の神様”と呼ばれる人物になろうとはお互い知るよしもなかったが二人が大阪から日本全国に商いの規模をすさまじい勢いでひろげ、やがて日本有数の企業となってからも、船場出身の商人として、互いに助け合う日々が来る。
(以下続く)







