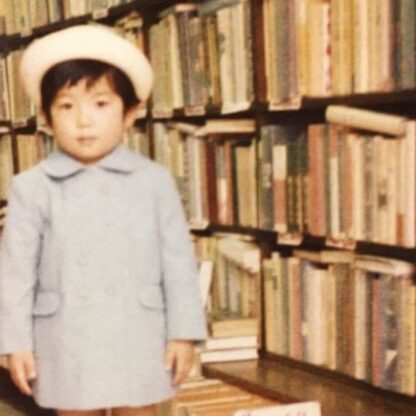季語道楽(51)”角川一家”の歳時記の傑作を… 坂崎重盛

ぼくが初めて手にした歳時記は誰の編のどんな本だったのだろうか。おぼろげな記憶をたどってみることにした。
新潮社の文庫版の歳時記は、その時々の句会の用のために、その季節の分(春るなら春の巻)をバラで入手したはずだ。
三省堂刊の「ホトトギス」?の歳時記は、シットリとした革装が気に入って、人にも差し上げたくて、神保町の本店まで買いにいったことが、二度、いや三度ほどあったはず。ところが、いま、その歳時記が手元に見当たらない。
机の前の本の間にはさまって薄い背を見せている季寄せは、ずいぶん前から手にしてきた。奥付を見ると昭和六十年刊とある。編者は角川春樹。正式タイトルは『新刊 季寄せ』とある。(元本は昭和五十一年刊)
角川春樹といえば、すでにご存知のように初代・角川書店の角川源義(ル げんよし)の息子で父の角川書店を継ぎ、新しいイメージの角川文庫、また角川映画でヒットを飛ばした出版界の風雲児。
父・源義は俳人としても著名だったが、春樹もまた俳句の世界で「読売文学賞」「蛇笏賞」を得ている俳人である。この春樹の編になる単巻歳時記にふれたい。本棚の一隅に“角川家”関連の文庫版の歳時記が積んである。
ちょっと興味があって、手元に積み直して高さを計ったら、ゆうに二十センチは越えていた。ちなみに、それら文庫本のタイトルを並べて、をメモしておこう。先に紹介した『新版 季寄せ』は略。
- 『新版 俳句歳時記』(春・夏・秋・冬・新年の五巻)。元本は昭和三十年
初版、「新版序」は角川源義、昭和四十七年の記。源義による歳時記への思いに接することができるのはありがたいが、あとでふれることにしたい。
- 『合本 俳句歳時記 新版』(昭和四十九年初版・角川書店刊。これは右記
の『新版 俳句歳時記』の合本。しかし、この新編集の合本には角川源義による「序」はない。
同じ歳時記で合本もダブって入手するのは……と思いつつも、ときとして、こういう微妙な違いがあるから歳時記集めは気が抜けません。
同じ合本ながら、編集部編ではなく、角川春樹、個人名での編が、
- 『合本 現代俳句歳時記』(一九九八年 第一刷・角川春樹事務所 発行)
この単巻歳時記については、このあと、すぐに少しくわしくふれるつもり。
- 『俳句 歳時記 第四版増補』(春・夏・秋・冬・新年の五巻・角川学芸出版編 平成十九年 第四版初版発行 角川学芸出版刊)「序」も編集部による。
- 『今はじめるひとのための 俳句歳時記 新版』(平成二十三年 新版初版KADOKAWA 発行 角川学芸出版編)これには、いわゆる「序」のようなものはなく、無記名の凡例に近い「はじめに」が一ページあるだけ。巻末の付録として「句会をやってみよう」「俳句Q&A」「古典の有名句」など、たしかに“今はじめる人のための”歳時記として編集されている。
ただ、余計なことながら、このサブタイトル的な題は、黒田杏子著『今日からはじめる俳句』(一九九二年・平成四年 小学館ライブラリー刊)を思い出してしまった。
もう一つ余計なことかもしれないが、すでに挙げた歳時記を“角川一家”の、と表したのは、はじめ角川書店版、つづく角川春樹事務所、角川学芸出版、そしてKADOKAWAと、角川系ながら、それぞれが版元が変わっていて、当然のこと、その編集方針も個々別々である。
ただ、ぼくなどの、句界やその周囲の状況にくわしくない人間にとっては、(やはり、源義、また春樹氏あってのお家芸、角川歳時記だな)という印象を持つのである。
さて、本題、その角川歳時記の「序文」、「まえがき」を見てみたい。単巻歳時記の『合本 俳句歳時記・新版』には、すでに記したように旧版にあった角川源義による「新版序」がないので、旧版による。源義氏の歳時記論と見ていいだろう。
「序」は、こう書き出される。
「歳時記は日本人の感覚のインデックス(索引)である」と詩人科学者寺
田寅彦が言った。
冒頭に寺田寅彦の言葉が引用されているのが嬉しい。寺田寅彦はよく知られているように、夏目漱石の子弟であり、著名な物理学者であり、若い時から俳句にも親しむ文人肌の科学者
で、彼の随筆を愛読するファンが今日も少なくない。「天災は忘れたころにやってくる」は寅彦の言葉とされているが、彼が東京帝国大学の地震研究所にいたころのエピソードだろう。
寅彦の句には「煙草屋の娘うつくしき柳かな」の句などは、句会などでは失笑を買っても仕方がない“大甘な”句で、「徒に凍る硯の水悲し」の“悲し”がぼくなどには気になるが「哲学も科学も寒き嚔(ルくさめ)かな」「炎天や裏町通る薬売」「雲の峰見る見る雲を吐かんとす」だったら、いただきます。とくに「雲の峰ーー」の句は、科学者ならではの観察の視線を感じる。
この寅彦の絵というかデッサンがまた、実にいいんですが、話を歳時記に戻さねば。寅彦の言葉に続く角川源義の「新版序」における季語論。
季語には日本の風土に生きて来た日本人の生活の知恵がある。季節感はも
ちろんのこと、倫理観、美意識、ありとあらゆる日本人の感情が短い文言
に収約されて季語となっている。
このあと、季語が連歌から俳諧に引きつがれ、芭蕉の時代では千にも満たなかった季語が、今日、その百倍にもなっている―ーと季語の増殖、新季語の誕生に言及している。
また、この角川『新版 俳句歳時記』が、昭和三十九年刊行の『図説俳句大歳時記』によって改訂、増補されたことを告げている。
序の文末で源義さんは胸を張る。
季語解説の補訂はもちろんのこと、例句は斬新であり、異色あるものと
なり現代の代表的俳人の代表作品をここに挙げることができたのは、限定
された文庫本のページのなかで、もっとも誇示してよいであろう。
―ーここまで書かれれば、この歳時記に例句として挙げられた作者は、大家はともかく、若手、中堅は自らの句を、それこそ“誇示”したく、この歳時記を求め、友人、後輩たちに配ったのではなかろうか、さすが角川の創業者、販売戦略にもたけてる、と邪推したくなる。
この源義のあとを継ぐ、角川春樹の編になる歳時記『合本 現代俳句歳時記』は、さらに春樹氏ならではの熱度が高く、ぼくの好きな歳時記の一巻でもある。その特徴にふれてみたい。
角川春樹編『合本 現代俳句歳時記』一巻を手にする。サイズは文庫版ではあるが、どっしりとボリューム感が手に伝わる。
巻末の、中国と日本の七十二候を並記した詳細な「二十四節気七十二候表」(これがありがたい)や「忌日一覧」、そして「総索引」を含めると、全千五百ページ余。
「序」のページを開く。編者の角川春樹による記。冒頭の一行目から、筆者の熱情が伝わってくる。ぼくが期待して集めてきた歳時記の「序」の文章の気配だ。引用したい。
日本の伝統文芸、特に詩歌や俳句にもっとも造詣の深かった山本健吉先
生が亡くなられて、今年で十年の歳月が流れた。その存在が大きかっただ
けに、残念でならない。
と。
すでに山本健吉についての部分でふれたように、俳句関連をはじめ、なにかと角川書店と縁の深かった、この文芸評論家に哀悼の意を表している。歳時記の「序」とてしは、珍しいことではないだろうか。
そして山本健吉の「日本文芸の根底に、詩歌がある」という言葉を紹介しながら、彼が特に、「短詩型文芸のよき理解者」であり、その信念のもとに「昭和の短歌・俳句の隆盛、発展に大きく寄与された」と顕彰する。
そして、ここからが、この歳時記の編者・角川春樹本人ならではの言葉だ。
私自身、まさしく詩歌こそ日本の文芸の根本だと思っている。私は永年、
実作者として俳句に携わってきた。作る立場から歳時記と携わってきた。
この人が、季語について語る。
俳句にいのちを与えてくれるのは、季語である。季語こそ普遍的ないの
ちであり、たましいであり、個性そのものである。
と、「一句の中心をなすものは季語である」と季語の存在意義を力説し、さらに、作句作法として、
俳句作品の出来、不出来の七〇パーセントは、季語の用い方に負うと言っ
ても言い過ぎではないだろう。
と言い切る。その季語を「選択し、分類し、そして集成、体系づけたものの歳時記である」と、“季語・命”歳時記の本質を端的に要約する。
編者の“歳時記愛”は並ではない。
たとえば、タイムカプセルに入れる本を一冊あげよ、と問われれば、人
によって聖書と答えるかもしれない。また国語辞典や、自分のもっとも好
む小説をあげる人もいるだろう。私の場合、一冊をあげるとすれば、それ
はもちろん歳時記である。
と。
こういう編者が主導した歳時記︱︱「実に多大な時間を費やしたが」「例句の豊富さと優れた作品の収録において」「もっとも参考になる歳時記ができたと自負している」。
きちんとした歳時記編集の労苦は、その編集担当者が等しく「序」や、「後記」で述懐するところではあるが、加えて、この歳時記がぼくに訴えかけるのは、
その季語にとってもっともふさわしい名句については、編者の判断で一句
だけ選び、例句の上にアステリスク(✻)を付けた。(傍点、坂崎)
と「編者の判断で」というところである。
多くの歳時記同様、例句の選択や季語解説は共同執筆者に負うとしても、その例句の中から「編者の判断で」あえて一句だけ選びとったというところが編者の“誠”として受けとれるのだ。ちなみにその季語にあたってみよう。
「浴衣(ル ゆかた)」。もちろん夏の
「人事」の項。傍題で、異名、関連語として「湯帷子(ゆかたびら)」「古浴衣(ふるゆかた)」「初浴衣(はつゆかた)」「貸浴衣(かしゆかた)」「糊浴衣(のりゆかた)」「藍浴衣(あいゆかた)」「踊浴衣(おどりゆかた)」「宿浴衣(やどゆかた)」。
︱︱古語でしょうか、“ゆかた”のみなもとの言葉、「湯帷子」は、ともかくとして、すぐにでも俳句につくりたいような季語がならぶ。古浴衣、貸浴衣、また、宿浴衣。
例句をザッと見てみる。十二句あるが、そのうちの気になる五句のみ、掲げます。
1 浴衣着て少女の乳房高からず
2 借りて着る浴衣のなまじ似合いけり
3 張りとおす女の意地や藍ゆかた
4 夕日あかゝゝ浴衣に身透き日本人
5 ゆるやかに着ても浴衣の折目かな
1の「少女の乳房」は、一瞬、ドキッとしますが、これは虚子の子が娘だけだったことのことでしょうか。だからか、虚子は俳句に向かう、女性を大切に育て、世に出そうとする。『立子へ』だ。これは、類いまれなプロデューサー能力である。
2 は「借りて着る」が肝(ル きも)でしょうね。
3 は「張りとほす」と「藍ゆかた」かな。
4 これは、句としては、? ですが「日本人」とあると、海外、たとえ
ばハワイとか?
5 気持ちのいい句ですね。とくに「ゆるやかに」が、なんともーー
ぼくのコメントなど、どうでもいいことでした。この句の中で、編者・角川春樹が丸印をつけた一句は、「借りて着る」の句、さすが久保田万太郎でした。
作者を記す。
1は高浜虚子、2万太郎、3杉田久子、いかにも、4中村草田男、5大槻紀奴夫、ぼくの好きな句です。
こんなことをしていたらキリもないのだけれど、もうひとつだけ、これまた夏の季語。「夏帯」といきましょう。8句あります。“そのうち五句を。
1 どかと解く夏帯に句を書けとこと
2 単帯かくまで胸のほそりけり
3 たてとほす男嫌ひの単帯
4 夏帯や一途といふは美しく
5 夏帯を解くや渦なす中にひとり
1の「どかと解く」もすごいけど、「句を書けと」で男性の句とわかる。作者は虚子。ーーさすがに、のうのうとノロケている。2も男の視線。どうも、男の句は、ともすると胸とか膝へ視線が行く。どなたが言う。“久米仙(人)俳句”でしょうか。
3これは逆に、凛としてます。しすぎているとも言える? ここまで句にすることはないのでは。そう、先の彼女の句の姉妹編の烈女・杉田久子。
4こちらは、道に迷った大女人の句でしょうか。“道行きの気配も、うっとりと。銀座で酒舗「卯波」を営んだ。鈴木真砂女。
5帯の「渦なす」が少々オーバーとはいえ、お手柄の自己観察、表現。この「渦なす」で、一篇の情痴小説でも生まれる磁力が野沢節子。春樹編者はこの句に。
ーーと、まあ、この春樹歳時記は例句の中、春樹さんが一句に限定して選んだことにより、“読む”楽しみが何倍にも増す。自分も対抗して選句している気になれるから。とても臨場感あふれる歳時記なのだ。しかもフェアーな雰囲気を受ける。
ぼくは、俳句の、頼りにする参考書の一冊として、この歳時記を傍に置く。もちろん、コレクションの対象としての、あれこれの歳時記は、それはそれで、おりふし撫でたりさすったりしていますけど。
ところで、たまたま神保町の古書店の店頭で、目にとまった角川春樹の『「いのち」の思想』を手にする。帯の背には「最初の随想集」とある。帯のコピーに導かれて「あとがき」を読む。
冒頭ーー(すべての文章の冒頭は大切。とくに短詩型実作者の書き出しは連句における“発句”にあたる。)ーーは、こうだ。
俳句は合わせ鏡である。
俳句は「見事に、作者の全人格を写し出してしまう」という。そして、続く言葉がカッコイイ。
俳句の方が、人間よりもしたたかなのであろう。
ご本人が、したたかで、謙虚な人間でないと、こういうつぶやきは生まれ出てこない。この書の「あとがき」は、こう終わる。
「いのち」の思想と気恥ずかしい題をつけたのは、切実で豊かな生き方
をしたいと思う願望に他ならない。
この書の中での編者・角川春樹の俳句実作の方法論を要約したい。
一 俳句は五七五のリズム感が大切。
二 映像が目に浮かんでくるような句。
三 作者の視点、思い、つまり自己の投影、感動はどう伝わるか。
そして、「櫻の魔性—-野性とロマン」の項で、自身の句を披露している。
御仏の貌美しき十二月
立春の不動明王艶めくよ
いっぽんの大きく暮れて花の寺
男来て花雪洞を下ろしけり
人骨散布いま深吉野は花得たり
「立春のーー」以下の句は、吉野への吟行で作られたもの。季節はもちろん春。
「父から受け継ぐ形で俳句を再開したとき、私の結社を“昭和のホトトギス”にしたいとしんじつ思った」角川春樹の絶唱といっていいのではないでしょうか。
父・角川源義〜〜角川のもとで俳句世界に深く関わり大きな影響力をもった山本健吉ーーそしてその流れを継いだ角川春樹ーーこの、“季語・命”の角川俳句に対し、前衛派の、季語依存への疑問をはじめ、反発があるのもまた、俳句のもつダイナミズムと考えられる。
俳句という、たった五・七・五、十七文字の極限の短詩型詩歌は一粒の小石であったり、巌であったり、さらには岩盤であったり、また、一粒の涙であったり、草の露であったり、池水であったり、さらには地球をおおう大海であったり、極小から極大であったり、際限がない。
日本文化は、日本の言葉は、この俳句という、季語、季題をよりどころとして、とてつもない表現形態を得たものである。そして、さまざまな考え、反撥はあるにせよ、その索引、インデックスが歳時記なのである。
翻って考えれば、同じ短詩型とはいえ、近現代の詩の世界に、俳句歳時記のような、四季の移り変わりや、その自然、時間のなかでの、人の営み、感情を総集した、イメージの索引、辞典、事典があっただろうか。
日本文化は歳時記を得た。