季語道楽(53)西日本歳時記ほか 坂崎重盛

と、よりみちはこのくらいにして、さっきから、妙に存在感のある函入りの歳時記が視界の隅に入っている。手にとろう。
- 『定本西日本歳時記』小原菁々子編(昭和五十三年・西日本新聞社刊)。
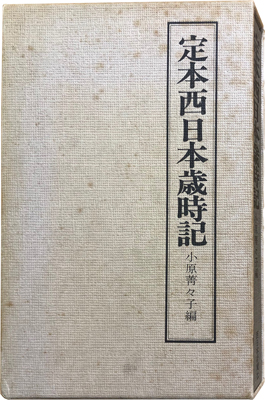
定本西日本歳時記 小原菁々子 編
“定本”の文字が、こちらに微妙な圧をかけてくる。
この歳時記は、ぼく自身が入手したものではない。大津在住の季題の物好き。古書店巡り好きのご仁が、この連載を見て贈ってきてくれたものだ。すでに記した珍本? 『ハワイ歳時記』も、このA氏から送付されたものだ。
A氏と京都の夜を過ごした時間を思い浮かべながら、ともかくページを開く。「序」は高濱年尾。昭和四十七年の記。“東京芝公園日活アパートにて”とある。本文、
俳句は季題の文学であります。
季題を通して、四季の移り変わりを描くのが俳句であります。その季題
は各地方によってそれぞれ独立しているものであります。
と、これは、厳父にして「ホトトギス」を率いた虚子の考えを踏襲する。引用を続ける。
かねてより西日本新聞紙上に、西日本季題として、特に採り上げて連載
されたものに小原菁々子君が筆になる、西日本歳時記があります。この度
それを一本として刊行することになりました。
(中略)
西日本独特の季題を通して、多くの人々は自分の思ひでを辿ることもあ
ると思ひます。
と記し。
斯く成りてなほいさぎよし梅雨晴るる 年尾
と献句している。まさに、正しい挨拶でしょう。
次の「編集のことば」。一部を引用する。
一、『西日本歳時記』は昭和三十九年六月から四十二年五月まで満三年間、
千四十八回にわたり西日本新聞に連載されたものである。
(中略)
- 本書はもともと新聞の片隅のささやかな読み物として始めたもので
あり、歳時記としてはあらゆる季題を網羅したものではなく、句作の友と
しては不備なものではあるが、一方、風土に根ざした特殊な地方季題を掘
り起こした点は在来の歳時記で閑却されていたところであろう。
まさに、宮部静生『季語の誕生』の“地貌季語”の書。菁々の「編集のことば」は、こう締めくくられる。
時代とともに消え去ってゆく古い風習や自然のありようを記録した小さな
ふるさと歳時記、郷土史の一部分としてでも見ていただければ幸いである。
東京下町生まれ育ちのぼくなどは、いまだに申し訳ないが、“西日本”といわれても、ただちに具体的なイメージが浮かばない。せいぜいが“関西”止まり。
久保田万太郎などは「箱根山を越えたことなんかないです」と、うそぶいていたというくらい。歳時記においても、もともとは京都。馬琴の時代になってやっと江戸のあれこれも歳時記に載るというくらいだから―—と言い訳をさせてもらいます。
本文の季題をパラパラとながめても、知的興味は刺激されるものの感情移入はありえない。どだい、こちらは他所もの。ただ、季題によっては知的興味は湧く。一月からページをめくってゆく。「鷽替え」「肥後の赤酒」「雉子酒」「熊本城のどんどや」「久女忌」「スルメかんピン」「絵踏み」「天草の椿」といった。季題に目が止まる。ほとんどの季題には、その地方の場所が示される。西日本といったって、長崎の季題は熊本人にとっては縁のないものかもしれない。
たとえば「絵踏み」(熊本県天草)。これが“隠れキリシタン”に関わることはわかる。関東者にとっては「踏み絵」、がなじみ深い。しかし、なぜ一月の季語なのか。解説を読む。
徳川幕府は一月四日から数日間、キリストや聖母マリアの画像を一般庶
民にはだしで踏ませる絵踏といった方法でーー
とあり、「一月四日から数日間」ということで冬の季語となったわけだ。知らなかった。
例句にあたりたい。
天草は哀話の多き絵踏みかな 宮崎草餅
そのかみの踏絵石てふ苔の石 古荘公子
絵踏みの絵掲げて古りし島の宿 橘一瓢
その地の人、あるいはそこに訪れた人でなければ生まれない句である。もう一題だけ。「天草の椿」(熊本県天草)。この地、とくに大江、高浜あたりは椿の大樹老幹が多く、しかも隠れキリシタンの里として知られているらしい。キリシタンには椿がよく似合う?
例句は六句掲げられているが、そのうちの四句だけ。
黒潮へ傾き椿林かな 高浜年尾
火の独楽を廻して椿瀬を流れ 野見山朱鳥
島の子に椿の寺と教へられ 菊池えい子
信徒身を投げし断崖紅椿 長野砂木
地方歳時記、地貌季語に関連しては、山本健吉の『地名歳時記』(全七巻・中央公論社刊)や『ふるさと大歳時記』(全八巻)が知られている。共に山本健吉監修。
西日本に遠出したので関東中心に戻る。標準語(死語?)ならぬ標準歳時記に。この歳時記、ページを開けば、その本づくり、編集・構成に配慮が行き届いていることがすぐに理解できる。
○『入門歳時記』大野林火監修 俳句文学館編(一九八〇年 角川書店刊・五六八頁)収録されている主要季語として約八百にしぼられているが解説、例句に加えて、選ばれた一句ごとに「鑑賞」の手引きが付されている。しかも掲げられている例句には、すべてルビがふられている。
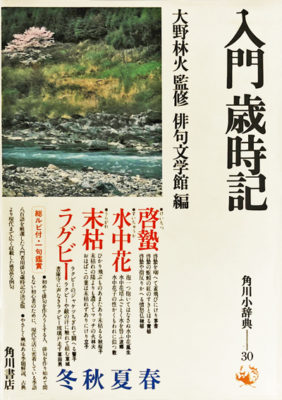
入門歳時記 監修:大野林火 編:俳句文学館 角川小辞典
この歳時記、ページをめくって、拾い読みしてゆくうちに、ある遊びを思いつく。鑑賞者は例句の中から一句を選んで、その解説をするのだが、まず、その一句の選出。それぞれの例句を読んで、ときに、(ぼくだったら、この句を取るな)と、異議をはさむ。そして、その鑑賞についても(えっ、そう読む?)と、疑問を発したりする。
俳句という、たった五七五の短詩型では、それを享受する側は、かなり勝手な解釈ができる。作者は、そんなつもりで作った句でも、それを読む側が、自分のイメージで、その句を解釈、鑑賞したりもする。俳句の半分? はそれを読む側の想像力、また創造力にゆだねられているといえる。
仮に句会で、いくら名句を出したとしても選句する側のレベルが低ければ、その句は誰からも選ばれることなく、その句会からは泡のように消えてゆく。つまり、この歳時記は読者も選句と鑑賞の楽しみに参加できるというわけである。
に、しても便利で頼りになる一冊。ところが、この歳時記の“ハンディ版”が出ている。文庫サイズ。元本が刊行された四年後。序文から索引まですべて同内容。季ごとに挿入されている扉写真まで同じという、気持よいくらいの改版ぶり。ちなみに所持している元本は初版から十四年で十二版、定価・本体二千円。お見事! ロングセラーだ。では、ハンディ版は? と奥付をチェックすると初版から十三年で十四版、定価・本体一四〇〇円、こちらも使用している。どちらか一冊を知人に謹呈しよう。
その大野林火が関わったもう一冊、こちらはさらにコンパクト。安住敦との共編による、
○『季寄せ 新装版』(昭和五十二年・平成九年新装版 明治書院刊)。典型的な、吟行や句会用の季寄せ。ただ、「本書の解説・例句は安住敦・大野林火が当った」というところが、門人や後輩まかせではない“責任編集”の季寄せといえる。これは、文字どおりであれば珍しいことではある。
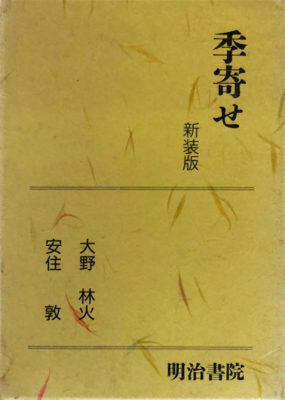
季寄せ 新装版 編:大野林火、安住敦 明治書院
単刊、季語、歳時記の山も切り崩し、とりあえずは、あと二冊だけ。一冊は岩波新書、
○坪内稔典『季語集』(二〇〇九年・三一〇頁)この人の俳句エッセイは、小路や土手をスキップ踏んで、遊んでいるような軽快な、フットワークの効いた文章で、いつも楽しく読める。パチンコで勝って(だったかな)念願の子規全集を買った話や、愛しい河馬の話などのエッセーを読んだ憶えがあるが、それらの本は、いま見当たらないが、
俳句は

季語集 著:坪内稔典 岩波新書
三月の甘納豆のうふふふふ
河馬を呼ぶ十一月の甘納豆
たんぽぽのポポのあたりが火事ですよ
と、一度目にしたら、なにか和風マザーグースのように頭に入ってしまう。この人の文章や俳句に接すると、「人間探求派」とか「難解俳句」だとかいった生真面目さが、かえって青くさく思えてくるから不思議だ。とにかく、こういうユニークなエスプリの効いた俳人による季語集というか、季語エッセイ。
巻頭は、岩波新書の手前もあってか、かなりマトモな季語についての説明がある。
一〇世紀の当初に成立した『古今和歌集』は歌を四季に分けており、その
四季観は現代に至るまで、もっとも基礎的なものとして存在する。俳句の
歳時記を開くと、たとえば、時鳥(ル ほととぎす)が夏を告げる鳥にな
っているが、それはまさに『古今和歌集』以来の伝統なのだ。
(中略)
季語は約束だと述べたが、季語の約束と本意(ほんい)という。春風は
そよそよと優しく吹く、というのが季語・春風の本意だ。
このあと、ネンテン氏は子規の句を例に出し、「本意」と「取り合わせ」についてのべ、
俳句を作る人は、季語の本意を取り合わせなどでずらす。写生という方
法も、今までは気づかなかった何かを見つけて季語の本意をずらす。
氏の俳句にくらべると、かなり行儀のいい、きちんとした俳論である。このあと、すぐにこの本の本意ではなく、真意を表明している。
この『季語集』は私が季語の本意をずらそうとしたもの、と言ってもよ
い。本意をずらそうとすることで、しばしば、私自身も生き生きとした気
分になった。季題を楽しむとは、実は、季語というめがねを通して自分を
見つめ直すことかもしれない。
本文は当然「春」から始まる。時候「立春」。冒頭で紹介される句は「立春のグラスは水を盛り上げて」(中原幸子)。ご本人の句は「立春の翌日にして大股(おおまた)に」。ー―ちょっと季節を先取りする感じが私は好きだーーと、おっしゃる。掲げる例句は
立春の米こぼれおり葛西橋 石田波郷(『雨覆(あまおおい)』一九四八)
立春や百号の絵の卵たち 能勢京子(『銀の指輪』二〇〇五)
この冒頭の一項に接しただけで、このあと掲げられる例句に期待が湧く。ネンテン師の選ぶ句だからである。また、例句の出典や年まで明らかにしているあたり、「うふふふ」ばかりではない学級肌のネンテン氏の真顔がうかがえる。いや、だからこそ「うふふふふ」なのか。
引用、紹介は一項だけにとどめるが、この稔典『季語集』、俳句の目利き、随筆家としての底力を、さりげなく披露する。
随筆的季語集といえばーーこの章の、この本を締めとしよう。
○『暉峻康隆の季語辞典』暉峻康隆著(二〇〇三年・東京堂出版刊・四五四頁)。この判型も大きく(A5判)、ハードカバー、部厚い季語辞典の存在を教えてくれたのは、この連載の伴走者、ベテラン文芸編者のI隊長である。

暉峻康隆の季語辞典 著:暉峻康隆
「シゲモリさん、あの、てるおかやすたかの書いた季語辞典、持ってる?」とのご下問。
「え、あの江戸文学、西鶴研究のてるおかやすたかが季語辞典なんか書いていたの。むかしカッパブックスだったかな、どちらかというと軟派というか、粋筆系の文章は読んだことがあるけど」「いやね、このまえ渡した、金子兜太と佐佐木幸綱の対談本(『語る 俳句 短歌』、司会は黒田杏子)に、三人が、その季語辞典はいいっていってるんですよ。ぼくもね、あの、てるおかやすたかが、そんな、めんどくさそうな仕事をするかなぁ、と思ってね」「そうですよねー、タレント教授のハシリみたいな、売れっ子でしたもんねー」で、これに関するI隊長の会話は終わり、別の話に移ったのだが、このあと、その季語辞典のことが気になってしかたがない。少し前からスマホで古書を探すことを覚えて、検索してみると、ありました! この本を「日本の古本屋」にのせている店が。住所を見ると、しかも都内。しかし、南砂町かぁ。土地勘のない町だ。電話をすると、JR、私鉄、どちらの最寄り駅から、歩いて十五分から二十分かかるという。
「バス停からは?」と聞くと「近くにバス停はありません」とのこと。
注文の手続きがめんどいうくさいし、一刻も早く、その現物を見てみたい。結論は、駅からタクシーで地番を伝えて向かうことに。
その地番につくと(こりゃ、歩いてきたら絶対にわからなかったわ)という住宅地の奥、しかも店舗ではなく倉庫のようなところ。電話しておいたので、本は用意しておいてくれたので即、GET! 美本である。それもそのはず、版元のスリップがはさまれたままになっている。で、七五〇円、安い! タクシー代を考えなければ。とにかく、I隊長から話を聞いた翌日に本を入手できたことに至極満足しつつ、頁を開く。
いわゆる「序」や「はじめに」という文字は目に入ってこない。いきなり「凡例」。その理由は一行目でわかる。
本書は、いまはなき暉峻康隆(てるおかやすたか)早稲田大学名誉教授
の遺稿、四百字詰原稿用紙一千余枚を整理したものである。遺稿は、晩年
の十数年にわたって執筆されたもので、生前本人の手により三二六項目の
季語を、各月ごとに一月から十二月まで分類されており、ほとんど完成さ
れていたが、さらに、死の直前まで再点検がなされていた。
この記は暉峻の学弟であり、元早稲田大学名誉教授、芭蕉、西鶴をはじめ、江戸俳諧の研究者、書誌学者。
「あとがきにかえて」も見てみよう。
昨年、平成十三年四月二日、暉峻康隆先生は九十三歳の御高齢で、「さよ
うなら雪月花よ晩酌よ」の辞世吟を遺されて逝去されたが、その直後にわ
たしは、遺族の暉峻由起子さんから一千余枚の大量の遺稿を託された。
(中略)
暉峻先生は西鶴研究の第一人者であるが、俳諧にも深い関心をもたれて
いた。本書は、そうした先生の俳諧研究のライフ・ワークというべきもの
で、晩年の十数年精魂をこめて、しかもご自身も十分楽しみながら執筆さ
れたものである。
西鶴を少しでも知る人は、西鶴が名だたる俳諧師であったことは知っているはずだ。一晩で二万三千 句を即吟したことは俳諧史では有名なエピソード。
雲英は続けて記す。
三百数十項目の季語のひとつひとつにわたり、そのルーツを万葉あたりま
で遡り、和歌、連歌、俳諧とたどり、さらに近代、現代俳句に及ぼうとい
う壮大なスケールのもので、末尾にはしばしば桐雨の号で、ご自身の俳句
も加えられている。
「桐雨」という俳号まで持っていたとは……知らなかったなぁ。
たとえば、ということで「夕立」を見てみる。
夕立 ゆうだち(ゆだち・よだち・白雨ゆうだち・夕立雲、ゆうだちぐも)
夕立にひとり外(そと)みる女かな 其角
夕立や家をめぐりて啼く家鴨 同
夕立や草葉を掴むむら雀 蕪村
と、まず江戸の句が示され、『万葉集』の、
暮立(ゆうだち)の雨落る毎に春日野の
尾花が上の白露念ほゆ
が「望郷の歌」として紹介される。まさに季語が、古くは万葉集から発していることを伝えてくれる。この和歌のあと解説は、江戸歳時記から虚子の『新歳時記』、山本健吉の季寄せまで言及、そして先の例句の鑑賞となる。たとえば二句目の蕪村の句に対して
素直な叙景句のようだが、群雀が草葉を掴むという強い表現で、夕立の激
しさを現しているのはさすがだし、また文人画家としての構図が感じられ
る。
という、読みをしている。
このあとすぐに、
わがつみのゆうばえとほき夕立かな 草城
追ふ如くをとめと走る野路夕立 友次郎
と、現代俳句を掲げ、作者のプロフィールを紹介、末尾に、
大夕立なすびトマトはこ躍りし 桐雨
と、自句を付けている。なんとも学究的にして、たしかに存分に自らも楽しんでいるオトナの芸だ。それにしても九十三歳で亡くなる直前までの執筆とは!文字どおりのライフ・ワークである。再度いおう、現代詩人、また現代詩の研究者に、このように季語集というイメージの百科全書を編もうとした人間がいただろうか、いるだろうか。「第二芸術」といわれた俳句の世界だが、その懐は深く、しぶとい文化を抱きつづけているのではないだろうか。
暉峻季語辞典は、ゆっくり楽しむこととして、いよいよ、各社が威信をかけての歳時記を一望することとしよう。そして、主に、その「序」、「まえがき」にあたって、編者の季語、歳時記観、また俳句理念を探ってゆきたい。わが、季語・歳時記道楽も、いよいよエンディングを迎えつつある。








