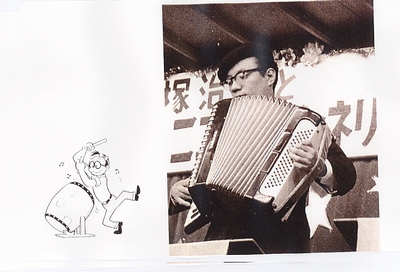私の手塚治虫(5) 峯島正行
二人の友から得たもの
頼りになる男
秋竜山と話をしていたときに、たまたま馬場のぼるに話が及んだ。秋曰く
「馬場さんが、木を一本描いて、その上を鴉が飛んでゆく、夕暮れらしい雲と山の稜線を描くと、俺たちが幼いころから経験している夕暮れのさびいい気分が、その単純な絵から湧いてくる、これが馬場さんの世界だ、この世界は日本人がだれでも持っている世界で、それをわずか数本の線で書いてしまう」
と言った。私はなる程な、と思った。私たちの血肉の中に存在する、日本の風土が醸し出した何者かを具体化したのが、馬場の漫画の線描なのであろう。
これは手塚の漫画にはないものである。
前にも言ったように、この馬場と手塚という別の世界に住む二人が、実に中のいい友人だった。単に友人であるばかりでなく、あの造物主のように青少年に崇敬されている手塚が、馬場には一目も二目を置いていたらしいのが、不思議だ。馬場の作品に対しても馬場という人物に対しても、手塚は一種の畏敬の念を持っていたように思えてならない。拙著「ナンセンスに賭ける」において、馬場のぼる論の章の冒頭で、このことを私が論じているので、少し長いが引用させてもらう。
「漫画界に何か問題が起きた時など、手塚が『馬場ちゃんどういってる?』とか『馬場ちゃんはどうしてる』などというのを、よく耳にした。つまり手塚はある面で馬場を頼りにもしていたのである。
手塚は天下第一等の人気漫画家で、その作品の量も膨大で、その収入も巨額、何もかも抜きんでた児童ジャーナリズムの巨峰であった。その手塚が馬場をかくも尊重するのが、最初のうちは不思議な感じがしなくもなかった。しかし時がたち、漫画というものが分ってくるにつれ、手塚のそういう態度も何となく理解できる気持ちになった。
手塚はご承知のように、熱いヒューマニズムを根底において、非凡な構想力と鋭利な論理により、科学的知識を駆使して、壮大な叙事詩を次から次へと、創造していった。
馬場のぼるの作品は、そのような手塚の作品とは極北をなすものであることは、私があらためて言うまでもない。馬場の漫画は、日本の風土そのものから生まれたような、土俗的、民話的なにおいがする、とぼけたほんわかした味わいの、なんとなく陽気なナンセンス漫画である。それを見ていると、唇のほとりから、筋肉がほぐれてきて、笑いが思わずこみあげてくるような作品である。その絵は頼りないような柔らかい線による、暖かい丸っこさが身上で、それが馬場独特の世界を創っている。
そしてナンセンス漫画だから、一枚もの,四コマ、こま割り漫画も、三,四頁がせいぜいである。その漫画がもたらす笑いの底から浮かび上がって来るのは、えもいわれぬ、甘い懐かしい情感と人間性の奥底にある何物かへの熱い共感なのである。
そういうものは、手塚がいかに知的な構想のもとに壮大な物語を、あの固い線で描いたところで、絶対に表せないものなのである。そして究極的に人々の心をとらえ、愛されるのは、知性と論理で築いた手塚の巨大な作品群より、馬場のほんわかした小さな抒情的な漫画の方かもしれないのである。
さすがに偉大なる手塚は、そのことを悟っていたに違いない。負けずぎらいで、自分に出来ないことはないと考えていた手塚も、その点ではシャッポをぬいだのだろう。そして、自分にはできないことを飄々とやってのける馬場への敬意となったのであろう。」
以上の文章は、私は一九九〇年に描いたものであるが、今でもこの考えは少しも変わってはいない。
「馬場の世界」を馬場が確立したのは、いつと探求している暇は、今はないが、比較的早い時代に創り出したと考えられる。それ以来、自分の世界を頑固一徹に守り、右顧左眄することなく、その世界を進化させてきたのだといえよう。
馬場は児童漫画家として登場し、児童漫画賞まで受賞しながら、その読者が成長するとともに、次第に大人漫画に転向し行ったわけだが、その後さらに転じて、絵本作家として、実績を上げた。
描く世界は時代物から現代生活に根差したものまでいろいろであったが、その間描く作風は、アイデアの生み方から、一本の線の引き方まで、一貫して変わっていない。馬場的世界の他には目を向けたことは、一回もなかったといってよい。どんな人間や動物が登場しても、一見、馬場の世界の一員とわかるようにしか、描かれないのだ。
そういう点から考えると、馬場のぼるは手塚治虫と反対の意味で甚だ頑固な男なのだ。 彼は一見飄々として融通無碍、夕暮の風にもなびきそうに見えるが、こと漫画の世界に関しては、頑固におのれを通して、決して妥協はしない男なのだ。
手塚は、馬場とは全く違う。手塚は時代の潮流、世の中の嗜好、嗜好の変動を確実に捉え、それに自己の作品を順応させるよう努力したと思われる。その上に立って、常に新規な分野を開拓しようとして、様々な実験的な試みを、強力に繰り返した。漫画の上でのみでなく、アニメ、映画、出版など様々な分野で、野心的に取り組んだことも、手塚の往き方を表している。
だから手塚は、学生時代から戦後の四十年以上にわたって、変動の激烈な児童漫画界の第一人者として君臨して来られたと言えよう。そういう手塚にとって、頑固にノウノウと構えている、馬場は驚異的存在であったのかもしれない。
馬場の自己の「らしさ」を通す、頑固ぶりを表すエピソードを一つ紹介する。
ローマの靴屋にて
それは前に書いたM・A・N・G・A旅行団の世界一周旅行した時である。馬場は、ローマに行ったら靴を買うつもりで、履き捨てにしてもいいような靴を、履いていった。ローマに着いた午後は自由時間になった。四、五人の仲間と、町に散策に出た。馬場はもちろんその途次、懸案の靴を買うつもりだった。その時、手塚が一緒だったかどうかは思い出せない。
商店街の目抜き通りの靴屋に、一行は馬場についてはいった。中年の男が応対に出た。
最近は変わったと思うが、ロンドンとか、ローマでは、伝統ある店の店員は一種の見識と、誇りを持っていた。彼らは代々靴屋の店員であり、コート屋の店員なのだ。そういう売り子は、客のほしい品物は、一足、あるいは一着しか出して見せない。それを身に着けると、体にぴったりなのだ。
「どうです」という風ににっこりする。これで大体商談は成立する。他の商品を見せてくれと言ってもなかなか応じない。「あなたにはこれがぴったりです」という。店員は頑固で、自信もあるのだ。
馬場に出された靴も履いてみると、なるほど足にはぴったりだ。しかしこの靴、瀟洒なデザインで垢抜けしている。万事その作品同様、地味に装うことの好きな馬場には、そこが気に入らないらしい。彼は、もっと普通の地味なものを要求した。
店員は「これがあなたによく似合う」と馬場の顔を見ながら言い張る。われわれ野次馬も、派手だといって特に目立つようなものではないし、「イタリア土産に少々派手なものの方がいいではないか」と、無責任な、店員の側に着いたような発言をした。
事実、私自身も、旅の戯れとまではいかないにしても、「ローマ」らしい靴を履いて旅をするのも一興ではないか、と思ったことは事実であった。
馬場は観念したように、その靴を履いて立ち上った。日本から履いて行った古靴はそこに置いてきた。そのあと我々も土産物などを買ってホテルに戻った。
夕食時、皆が食堂に集まった時、馬場が我々仲間に向かって「結局ね、あの靴は返してきたよ」と言って足元を見せた。日本から履いていった古靴を履いていた。ホテルに戻って一人になってから単身靴屋に戻って、靴をかえしてきたという。
「どうも私には派手なんでね」
前掲書でこれについて私は次のように描いた。
「店員も店員なら馬場も馬場だと思った。既にはいて街を歩いた靴を引き取って、置いてきた古靴をはかせて返す店員の頑固さにも驚いたが、地理不案内の夕暮れのローマの町を一人で返しに行った馬場という人間を見直す想いだった。あの気の優しい馬場が、自分らしからぬと思ったものへの厳しい峻拒、今まで知らなかった彼の正体を見た思いだった」
日本にいる限り毎日、編集者たちの多くの要求、催促に立会い、そしてアニメの担当者と、雑誌編集者とが、身柄を取り合いになっている手塚が、ほっと息をついたのは馬場との付き合いの瞬間にあったと思うのは、私だけだろうか。
西欧伝統の女性美の探求
小島の親分気質、彼が醸し出す遊蕩気分も、手塚に一息つけさせるものがあったろう。そして何より小島の描く『女』のエスプリも彼の学ぶべき対象だったはずだ。
小島の描く女性は、当時の、グラマーブームというか、肉感的な女性が好まれた、風潮にピッタリはまって、人気が沸いた。しかも小島の描く女性は、単に肉感的であるのではなく、ルネッサンス以来の西洋絵画における、女性画の線描に通ずる何かがあるように私には思えた。それが戦後の西洋文化と親しむようになった男たちの欲求に、マッチしたのだろうと思う。
その点でも手塚は小島に学ぶことが多かったと思われる
小島がそんな「おんな」を描くまでには、それなりの過程があったのだ。
もともとオンナ好きの小島には、女を描く才能が天性としてあったことは確かであろうし、前述のように自ら勉学したのも事実だが、それに磨きかけさせたのは、編集者としての吉行淳之介だった、と私は思っている。
昭和二二年、小島功は馬場辰雄、中島弘二、関根義人と、独立漫画派というグループを結成したが、戦後の娯楽雑誌創刊ブーム、いわゆるカストリ雑誌の続出によって、何とか漫画で収入を売るとともに、仲間も次第に増えた。八島一夫、金子泰三、あんど利一、赤川童太、やなせたかし、山本一郎、イワタタケオ、長新太、茨田茂平、針すなお、久里洋二までが加わり、昭和二六年には、銀座二丁目、並木通りの角にあった、「エチュード」というクラシック喫茶店の二階に、事務所を借りることができた。
戦後多くの若い人たちによって、漫画グループが出来たが、いつのまにか、消えてゆき、独マンが一つの若い勢力として残ったのである。このような発展ぶりは、リーダーシップのあった小島の力によることが多い。
若い彼らは、共同で、仕事をして、その収入が入ると、銀座裏を飲み歩き、果ては赤線、青線に流れるという、無頼で、原始共産制のような生活をしていた。
当時の様子を私は次のように描いた。
「当時独マンは娯楽雑誌の漫画欄に合作することが多かった。合作が多いということは収入もみんな変わらないということである。みんな独身で収入も変わらないから人の財産も自分の財産も同じというような、でたらめな共同生活であった。合作作品の原稿料が入ると、徒党を組んで、銀座うらを飲み歩き、金が残れば、「玉ノ井」「鳩の町」などの赤線に繰り込んだ。『当時、夕方、事務所に行くのが楽しかった原稿料が入ると、とことんまで飲んだ。飲む金がないとモダン日本の編集をやっていた吉行淳之介さんのところへ飛んで行って、金を借りた』
と小島功は語っているが、彼等がこのころ最も親しくしていた編集者の一人が吉行淳之介であった。彼らの理解者であると同時に遊び相手でも会った。「吉行の注文で『モダン日本』の合作漫画や単独漫画せっせと描いた」(吉行淳之介全集別巻三 昭和六〇年 講談社)
この吉行と知己になったことが、小島を小島らしく育てたという重大な意味を持っている。当時を小島自身に語らしめよう。
独マンの事務所に
「いつからか長身で背をチョット丸めた編集者が現れだした。白皙な面に目の黒さと唇の紅さが目立つ人だった。吉行淳之介という「モダン日本」の編集者で、仲間の評判では、凄く漫画のわかる人だという。そしてすごく酒が好きで、麻雀も強いとか、年は三つ四つ上らしいが、たちまち仲間言葉で付きあうようになった。
吉行さんがボクに初めて女を描かせたような気がする。いや自信を持たせたのかも……。
よくカラーページの扉絵を注文してくれたからだ。『これいっぱいに女を書いて』という。当時駆け出しの漫画家にそんな注文は皆無の時代であったから、ボクもその気になって書いたのである」(前掲書)
吉行はこのとき小島の将来を見通していたのだ。吉行に見いだされた漫画家の数は多い。夭折してが、天才と言われた芳の次郎、赤川童太、鈴木義司、富永一朗など吉行が最初発見した天才である。小島も吉行が育てたのだ。彼は新人発掘の天才と言われた。
もう少し小島の文章を続ける。
「モダン日本社は新富町にあって、有楽町駅からの往復にボク等の事務所の前を通ることになる。退社後は自然一緒になって飲み歩くことが多く、吉行さんの言う『なんとなくウマが合ったのだろう』ということだろう。酒量は同じように強かったからかも知れない。ただ違うのは酒の質で彼の方は色酒であった。酔いがあるところまで来ると話が女のことになり、いつしか赤線に……そして『えへへへ…行ってみよう』ということになる。
ボクは女の方は意外と奥手であって、そのころようやく面白くなってきたばかりだからやっぱり誘われてから腰を上げる次第で、意馬心猿に違いなく、確か誘われて断った覚えがない。
一時期毎晩のように仲間と飲んでいたが、ある日「これ読んでみて」と一冊の小誌を渡された。三田文学であった。中に『谷間』という小説が載っていた。吉行淳之介という活字と…。このときは驚いた。そんな馬鹿な、あんなに飲んでて、あんなに遊んでいていつ小説なんか書けるのか、しかも小説の話なんか一度もしたことがないのだ。
その小説(筆者注・芥川賞候補になった)にはすこしの気負いのない何時もの彼の姿勢そのままの語りである。大きな一撃くらった気分で呆然とするのは当然であろう。
中略
初め編集者として付き合い、次に仲間として、そのうちにボク達の世話をやく兄貴と変わっていった。
金のない時程人間はムリをして遊びたがるもので、ツケのきく飲み屋からツケのきく娼家へと流れていく。その赤線のツケは後日『この原稿何ページ、早く書いてよ、原稿料はあそこへ払うのだからエヘヘへ…』という注文になって来る。
中略
この町は「原色の街」のモデルなのだが、一緒に遊んでいながら、あの小説を書く才能と観察力にはショックを受けた。こっちもしっかりせにゃ――といたずらに娼婦の体をまさぐってきたせいか、その後あんな女ばかり描くようになった」(前掲書)
「あんな女ばかり」というのは謙遜で、そのお蔭で女の色気を描かせたら、右に出るものはないという技量を磨いたのだ。吉行も一緒に遊びながら小島に『女』を学ばせていたのだ。漫画の描き方について吉行とやりあうともあったらしい。吉行自身が次のように 述べている。
「私は漫画の鑑賞に自信をもっていてずいぶん勝手な意見を述べた。小島功など、何度も腹を立てたらしい。しかし、『あいつの言うことは、どうも当たってところがあるようだ』思い直して、腹の虫をおさめたという」(拙著ナンセンスに賭ける)
こうした経緯で、小島はハイセンスな女を描く漫画家として、次第に頭角を現した。昭和三三年週刊サンケイに「黒猫ドン」アサヒ芸能に「仙人部落」を連載しはじめ、一躍人気作家となった。其の後旺盛な活動期にいり、「俺たちゃライバルだ」(週刊漫画サンデー)「日本おかあちゃん」(週刊マンガサンデー)などの代表作を描き、文春漫画賞も受賞、昭和三五年から約十年続けた「週刊漫画サンデー」表紙絵は、漫画大絵巻となった。小島のライフワーク的業績となった。
手塚の交友したころは、小島の最も脂ののった上り調子の時であった。吉行という後ろ盾のもとに、女修行をした小島の作品と人柄は、全く手塚にない世界であったから、交友の間にどれだけに刺激と影響を、自然のうちに受けたか、測れないものがあったと信ずる。
もう一つ、小島と手塚を結びつけた要因に、
小島の一世一代の、仕事であった「日本漫画家協会」の設立ということがあった。
小島が昭和二二年から初めた「独立漫画派」は、二十年の間に、着実に成長し、その同人には九里洋二、長新太、のような芸術派から、娯楽雑誌に執筆する娯楽作家まで、同人がバラエテーに富んでいた。これも小島の人柄と、画風によると思われたが、ともあれ、出発いらい二十年を超えた、昭和三十年代には、同人の数も二十人を超えた。
昭和三一年には同人雑誌「ガンマ」も発行し、高い評価を得た。
ところが、昭和三三年、九里洋二が、谷口、杉浦幸雄、加藤芳郎に続いて、第四回目の文春漫画賞を受賞し、ついで第五回目の賞を長新太が受賞する、ということも一因になっていると思うが、独漫の中がぎすぎすし始めた。最後には独マンは、親睦団体としてゆくか、研究団体としてゆくか、の議論を巡って同人の意見が分かれた。
小島としては、そのごたごたを収めて、平和に戻してやってゆく自信があったが、小島はあえて、昭和三五年、解散に持って行った。その解散パーティーが、新橋で催されたが、その帰り、どういうわけだか、小島と私と二人だけで、銀座方面に歩いて行った。その時、小島は、次のように私に言って聞かせた。
「僕はね、一口に漫画と言ってもその範囲は広いだろう。子共漫画もあれば、幼年漫画だってあるしさ。大人漫画だって、我々のように新聞雑誌に描く者もあれば、底辺と言っちゃ悪いが、娯楽雑誌専門の描き手だっている。
また地方の新聞、雑誌に書いている人いる。
僕はね、そういう漫画を描いて暮らしているすべての人たちが連絡、交流す大きな団体を作ることを夢見ていた。その為に独マンの存在など、小さなことだと思ったのさ。
それに漫画の著作権の問題、健康保険、税金の問題、などなど社会福祉的な問題がこれから、ますます大事になってゆくだろう。その問題の解決のためにも機能的な、全漫画家を網羅する職能団体の必要性が、目の前に迫っている。だからそういう団体を作るために、俺はこれから働くつもりだ。宜しく頼むぜ」
そういって、小島は銀座の夜闇に消えて行った。
小島をはじめとする、有力な独マンの漫画家は、その後、一,二年のうちに漫画集団に加入した。漫画集団に入っても、小島の漫家の職能団体の設立の夢は燃やし続けた。漫画集団は、職能団体的な存在とはとは全く関係のない、社交的な友情団体みたいなものであった。
昭和三八年の春のある日、ゴルフ好きの漫画集団有志が、飯能ゴルフ倶楽部でゴルフを楽しんだ。上がって、食堂に集まり一杯やった。メンバーは加藤芳郎、塩田英二郎、岡部で冬彦、それに小島である。
ゴルフから上がって、食堂で一杯やった。酔いがそろそろ回ったころ、小島が何気なく年来の持論である、漫画界を網羅した職能団体の必要を、説いた。いっぱい入っているから熱っぽく執拗に語ったらしい。
みんな賛成だった。こうなると、すぐに実行にかかるのが、漫画集団の連中のやり口だ。
加藤が
「そういうことなら西川タッチャンに頼むのが一番だ」
といった。さっそく、ゴルフ場から、四谷の西川辰巳邸に、車を飛ばした。彼らの話をきいて、西川は「そういう話なら、ひと肌もふた肌も脱ごう」と応じた。江戸っ子で、事務の才に恵まれた西川は、それから疾風迅雷の如く活動した。小島は、手塚に児童漫画家の糾合を依頼し、これに応じて、手塚も動いた。
五月三日には、日本漫画家協会発起人大会を開き、以後半年、一二月一五日に創立総会を開くというスピード振りであった。
理事長に、近藤日出造、常任理事に西川辰巳、古い児童漫画家の秋玲二を並べてバランスを取った。理事その他の役員に、思想的な左右両派、年齢層、児童漫画から政治漫画まで、中央にいる作家から地方作家まで配慮した巧妙な配列に、我々は西川ならではの行き届いた神経を感ぜずにはいられなかった。だが、その西川の背後には、発案者の小島、児童漫画の実力者手塚治虫がいて、協力して屋台骨を支えたのであった。両者とも理事として、設立後も陰に陽に、大きな役割を果たした。
協会はできたが、漫画集団は依然と変わらぬ、姿を保った。協会設立後、一年して手塚は、漫画集団に入って、馬場や小島のみでなく、多くの漫画家と交流したのは、言うまでもない。手塚はあの多忙な中にあって、漫画集団の行事や会合には、結構マメに出席して、仲間との交流を楽しんだ。
三つの戦争漫画
私が、手塚と知り合ったのは、手塚がまだ漫画集団に加盟していない、おそらく昭和三七年と思われる。最初如何にして手塚に接触したか、もう記憶が無くなったが、おそらく小島にあるところで紹介され、その後手塚に大人向けの原稿を頼むために、手塚を訪ねたのではないかと思う。
その頃は、児童漫画と現代でいう大人漫画の世界とは、まったく別の世界であった。
我々は漫画と言えば、今日でいう成人漫画、大人漫画をさしていた。子供漫画は子供の読むもので、子供雑誌や単行本をお小遣いで、あるいは親に買って貰ったりして、読むもので、大人は読まない。
大人の漫画は新聞、雑誌に載っていたが、それはその新聞なり、雑誌の、紙面を彩るための、アクセサリー的な存在で、それを目当てに新聞、雑誌を売ったり買ったりする存在ではなかった。
しかし世の中には漫画好きな人もいて、連載漫画を毎日、毎月楽しみにしている読者もたくさんいた。中には横山隆一のフクチャンのように、国民的アイドルになって、だれ知らぬものない存在になった連載漫画もあった。
だから、漫画というものは、新聞の、政治、時局の動きを材料とする、解説的な漫画や、社会面に載る、四コマの連載漫画であり、雑誌でいえば、一頁、二頁の連載漫画、雑誌の巻頭に口絵として、組まれた漫画特集に使われる漫画、その中には多色刷りもあったが、それらが漫画の一番の市場であった。
子供の世界のように漫画専門の雑誌や、娯楽的漫画の単行本はなかった。あっても稀な存在であった。
我々編集者も、新聞や雑誌で見る漫画は知っていても、子供漫画は、とくに読むわけではないから、子供漫画の世界は全く無頓着、無関心であった。私自身がそうであった。
テレビの「鉄腕アトム」の人気や、手塚の年収の高さが、「絵描き」の中で日本一なったというような報道などで、手塚が児童漫画の第一人者であることぐらいしか、知らなかったのだから、今から思えば、隔世の感があった。大人漫画と、子共漫画を同時に書くなどというのは、殆どなかったし、あってもほんとにまれな事であった。
しかし手塚が、その稀なこと始めたのは割合に早かった。子供漫画家の手塚が、大人漫画を描いたのは、昭和三〇年まで遡ることができるのだ。
昭和二九年、三〇年頃になると、新聞、雑誌の漫画を喜ぶ読者層が増え、一流新聞,総合雑誌で、漫画特集などを出すと、読者が飛びつくという現象が生じてきた。
漫画の人気作家が、文芸作家と並んで、文士劇の舞台に出て、それがマスコミ報道されたり、漫画集団が、夏の鎌倉のカーニバルに参加したり、大劇場のショウの舞台に出たりして、それが報道され、漫画家は世の人気者になった。そういうことも漫画の人気をあおったに違いない。
それでだれが言い出したか、世は漫画ブームと言われ、折からの神武景気と言われた戦後の経済的な復興の波にみのって、漫画専門の雑誌が出てきた。
すなわち前号でも述べた、文芸春秋社の「漫画読本」である。何かの行事で、横山隆一が、文春社長池島新平と旅行した時、汽車の中で、「文芸春秋の別冊をだし、それを全部漫画で埋めるのさ」と横山が漫画雑誌の案を、池島に述べ立てたという。
「うん面白い案だが、売れるかなー」
池島は疑心暗鬼だったが、昭和二九年一二月、実験的に「文春別冊、漫画読本」として発売すると、十七万部刷ったものが、数日で売りきれになった。
一月に二号目を出すと、また売れた。のちには、それが独立して、月刊誌となった。
「漫画読本」が出ると、「週刊読売」もその別冊として「漫画読売」を発行した。
読売と漫画はつながりがあった。昭和の初期、正力松太郎が、読売の経営を引受けた時、編集部内に漫画部を創設、漫画を読者獲得の手段とした、という経歴もあった。近藤日出造、杉浦幸雄も、漫画部のぺーぺー部員として、勤務したことがある。杉浦はすぐやめたが、近藤は戦後も読売で倒れるまで、仕事を続けた。
そういう伝統があるので、それに乗って漫画雑誌を出せたのだろう。
このころの漫画ブームに載せて、各種のマスコミでは漫画特集や漫画ページの増大化を図るようになった。
早速昭和三十年には、文春漫画賞が設置され、第一回受賞者に、谷口六郎が決まった。手塚は谷内を評して「郷愁を詩いあげる漫画詩人」(ぼくはマンガ家)と評した。谷内は創刊以来、死ぬまでで週刊新潮の表紙を描き続けた。
こういう賞の受賞ということは世の新人漫画家、漫画志望者に火を点け、その数も激増し、飯沢匡を校長に頂き、一番権威があるとされたアサヒグラフに投稿欄「漫画大学」をはじめ。各雑誌、新聞の漫画投稿欄は、花盛りとなった。編集する側も、そこから金の卵を産ませようと、投稿欄の充実を図るようになっていった。
貪欲な編集者は、漫画家を子供漫画の世界からも、タレントを物色し始めたのである。
手塚は、その第一号として、「漫画読本」、「漫画読売」の双方から、に引っ張り出され、双方に作品を発表させられたのだった。児童漫画の方では、神のような存在で、絵画部門の所得ナンバーワンになった大家も、考えてみれば、大人漫画では全くの新人であった。
「漫画読本」の方では、まだ月刊誌に昇格する前の三十年七月の、文春増刊漫画読本に、「第三帝国の崩壊」がのった。これが大人漫画の処女作と言っていいかもしれない。翌月八月には「昆虫少女の放浪記」を掲載した。
一方「漫画読売」には三十年十月五日創刊号に「ああ平和の女神」翌三一年三月五日号に「兵隊貸します」を掲載した。
この四本のまんがのうち「第三帝国の崩壊」
と「ああ平和の女神」「兵隊貸しますの」の三本は、いわゆる「戦争漫画」である。独裁制、絶対権力者への嫌悪と戦争否定から生まれるアイロニーを、SF的世界において描くブラックユーモアである。このテーマは、その後、描き続ける、手塚漫画の一番大きなテーマであり、最大の力量をここに注いだ。仮にこれを『アンチ・ウオー』作品と名付けておこう。
『ああ、平和の女神』はたった二頁の作品である。当時の大人漫画の世界では、二頁の作品は普通だったのである。その内容を簡単に紹介すると、何時の世か、平和を愛する二つの国があった。平和を愛しすぎるため、平和のための二つの国の女神は、平和のための戦争を開始した、しかし両国とも負けず劣らず、ついに両国とも滅びるという話である。
「兵隊貸します」は人口過剰に悩む国が、強権を以って、人民を兵隊にして、海外派兵して金をとる商売を考え、一級品から三級品、はんぱ者クラスに、分けて海外に売り出す、売られた兵士が、ウラニウムの鉱山を発見、その金で、前兵士を買い取り、政府を倒し、平和な国に戻るが、時がたつとまたもや人口過剰になり、再び兵を売り出す事業を始める……、という話である。
漫画読本の「第三帝国の崩壊」は題名からしてわかるように、独裁国家の滅亡を描いた昨品だ。ドイツのヒトラーはナチスドイツを第三帝国と称し、ゲルマン民族こそ世界を支配する優秀民族だとし、その独裁によって世界制覇めざし、周囲の国を侵略したのであるが、この作品はそのパロデーと言えよう。
いつの時代であるか、その国では、強力なロボットによって人民を独裁者の言うなりに支配するが、人口増加によって大内乱が起こり、帝国は破滅にする、独裁者は自分の命だけ残そうと「人工冬眠地下壕」に避難するが、目覚めたときは原水爆の爆発によって、すべての人間が死に絶えていた。残っているものは独裁者とロボットだけだった、という恐ろしい話である。
もう一つの作品「昆虫少女の放浪記」は、戦争漫画ではない。一匹の昆虫が、つぶさに幸福そうな人間世界を観察するが、人間の世界もまた生き難い苦しい世界とわかり、心を入れ替え、昆虫らしく生きることを決意するという話で、虫の世界とか、怪獣の世界とか、異種の世界と人間世界と比べて生きることのペーソスを描くという、手塚の漫画手法を代表する作品である。これを「異種世界譚」と名付けておこう。
この四作品の後、いかなる芸術的作品画を描いたか.それが次の問題である。(続く)