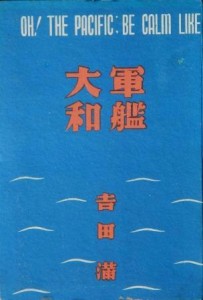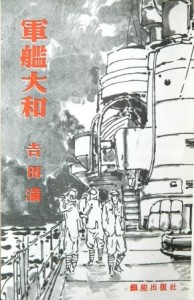書斎の漂着本 (43) 蚤野久蔵 軍艦大和
わが書斎にやってきた本の中にはどこで手に入れたのか思い出せないものも多い。これもそのひとつ、昭和24年、銀座出版社発行の『軍艦大和』(吉田満著)である。
著者の吉田は東京帝大からの学徒出陣で、海軍予備学生となり海軍電測学校に入学した。大学を繰り上げ卒業後、電測学校を出ると同時に少尉に任官、戦艦大和の副電測士として沖縄特攻作戦に参加した。「特攻」の名のもとに片道燃料だけの、もとより生還を期すべくもない出撃だった。
広島生まれの私は、母の二番目の姉が呉に嫁ぎ、大和が建造された旧・海軍工廠を見下ろす宮原通で酒店を営んでいたから、子供のころに遊びに行くたびに「あの下のドックで戦艦大和が建造されたんよ!」という自慢話を聞かされた記憶がある。その後も同じドックで建造された当時世界最大となる初の10万トンタンカーを見に行ったら「戦艦大和より大きいのは大したものよねえ!」といわれたものの(大きすぎて)ピンとこなかった。あのときは小学生だったなあと<あたり>をつけて調べてみたら「ユニバース・アポロ」で、昭和31年に現在のIHI呉造船所で建造されていた。
わざわざ昔の記憶を紹介したのは<大和は戦艦>という思い込みがあったからで、古書店の均一棚で『軍艦大和』が目に留まったのも、題名への違和感からだ。もっとも軍事用語では「戦艦は軍艦の一種」なのであって、しかも「最も強力な大砲と、最も頑丈な装甲を備えた巨艦」が大事にされた<栄光の日々>は過去の歴史となり、いまや最新鋭のハイテク・レーダーや優れたコンピュータ・システムを装備した「イージス艦」の時代なのだ。
戦艦大和をあらためて考えるきっかけになったのは鬼内仙次の『島の墓標―私の「戦艦大和」』(創元社、1997)の書評めいた雑文を書いたからである。その数年前に仕事で出かけた徳之島で戦艦大和の慰霊碑を案内してもらったことや、NHKの特別番組で沈没場所を突き止める水中調査のドキュメントを見たことも関心につながった。『戦艦大和ノ最期』や『鎮魂戦艦大和』をはじめとする吉田の著作だけでなく、水中探査の写真集など本棚の一角が「戦艦大和関係」で埋まった。戦後、日本銀行に勤務した吉田が国庫局長時代に補佐した作家・千早耿一郎(ちはや・こういちろう)の『大和の最期、それから』(講談社、2004)などが書評で話題になるたびに読んだが、まだ『軍艦大和』はなかったように思う。
『軍艦大和』は四六判の縦を少し小さくした大きさで182ページ、表紙にセロファンをかぶせたのを、見返しの「きき紙」で直接押えてある。セロファン自体は劣化して右上など一部にしか残っていない。表紙だけではわかりにくいだろうから全体を紹介すると英文はOH’ THE PACIFIC:CALM LIKE UNTO THY NAME! で、右の裏表紙に3行に白抜きで分かち書きされた「太平洋よ その名の如く しずかなれ!」という意味である。
表紙の装丁は武蔵野美大で長く教授をつとめた洋画家の三雲祥之助で、濃い藍に白い波をあしらっている。見返しにはやや抽象的な青年群像、扉には静謐に思える艦上人物図が共に洋画家の向井潤吉によって描かれている。同じ京都市の出身であるがその縁でタッグを組んだわけではなさそうだ。群像の青年は死んだ人物を抱え、あるいは倒れ、両手を広げて何かを叫び、顔を覆って慟哭する姿なのに対し、人物図のほうは双眼鏡を眺めている人、そこから別れた人もポケットに両手を突っ込み、ゆっくり歩き去る構図である。戦時中は従軍画家協会の会員として戦争画を手掛けた向井だが、あえて平時の艦上風景を描いたのもそれなりの意味もあったのだろうか。群像が<動>ならこちらは<静>である。晩年は古い民家の絵を描き続け「民家の向井」といわれたことを思い合わせると感慨深い。
右の扉に続いて「在りし日の軍艦大和」、「大和轟沈の瞬間」のモノクローム写真2枚に「軍艦大和建造秘録」1ページ。『軍艦大和』と『軍艦大和その後』が収録されて182ページで定価は150円である。24年8月10日に初版発行、15日に再版、手元の3版は20日と、立て続けに発行されたことが分かる。
千早は『大和の最期、それから』で、当時、世界一とされた戦艦大和を沖縄へ出撃させた「天一号作戦」は戦争末期の戦況悪化の焦りから参謀本部が編み出した神風特攻に対して海軍の面子や見栄もあって採用されたという。駆逐艦30隻分の重油を食らう巨艦の維持はいよいよ困難で、「大和」は、重油を食らう巨体であるがゆえに邪魔者扱いされての出動だった。オトリとなって敵攻撃の矢面に立ち、来るべき「一億総特攻の模範」となれという連合艦隊参謀長からの指令を大和に乗り組んだ第二艦隊の伊藤整一司令長官は苦衷のうちに受け入れざるを得なかった。
大和轟沈後、米軍機の執拗な機銃掃射を受けながらも無数の将兵の遺体が浮かぶ重油の海を漂流すること4時間。駆逐艦に救助され、かろうじて生還した吉田は、漂流中に受けた頭部の裂傷のために入院した。だが完治しないうちに、みずから希望して退院し、特攻を志願する。「死に後れた」という気持ちに責められ続けていたが、命じられて赴任したのは高知県須崎にあった最大の「人間魚雷」基地の対艦船用電探(レーダー)設営隊長で終戦を迎えた。吉田はそのまま須崎に留まった。小学校の分教場の女教師の一人が身重で、代わりに教師を頼まれたためだが、敵が吉田を見つけたら生かしてはおかないだろうという集落民の心配もあった。もうひとりの女教師と元気な子供達に囲まれてはいたが、吉田は敗戦の<意味>を考え続けた。須崎から南南西、足摺岬のかなたに徳之島がある。さらにその北西の海底深くに大和と3千余名の戦友が眠っている。須崎は遥かな海からの<呼び声>が届く場所でもあった。
ようやく9月中旬、吉田は父母の疎開先の東京都西多摩郡の吉野村(現・青梅市)に帰郷した。恵比寿の自宅は空襲で焼けていたからだったが、偶然、近所に疎開していた作家の吉川英治が父と疎開仲間として旧知だったので訪問した。最初は問わず語りではあったが吉田から大和での話を聞いた吉川はしまいには涙を流し「君はその体験を必ず書き残さなければならない。それはまず自分自身に対する義務であり、また同朋に対する義務でもある」と送り出した。帰宅すると吉田はただちに筆をとった。わずか1日足らずで一気に書き上げたのが代表作の『戦艦大和ノ最期』の草稿である。題名にあるように全文が文語体で書かれていた。友人の何人かがそれを筆写して回覧したがそれで終わった。
この年の12月、吉田は日本銀行に入行して統計局に配属された。翌21年3月、外事局に異動したが直後の4月1日に評論家・小林秀雄の訪問を受けた。「エイプリルフールのいたずらにしては、手のこんだことをするやつがいる」と思いながら面会所に行くと、まぎれもなく小林本人がいて、友人が筆写した草稿を持っていた。小林は、いま編集責任者として準備中の『創元』第一輯にこれをいただきたいと言った。小林は「自分の得た真実を、それを盛るにふさわしい唯一の形式に打ち込んで描くこと、これが文学だ、それ以外に文学はない。だからこの覚え書きはりっぱに文学になっている」と口説いた。吉田は、発表するつもりで書いたものではないが、もしその価値があるのならお任せします、と答えた。
進駐した占領軍は、真っ先にすべての出版物についての事前検閲を行っていた。戦勝国にとって不利と判断されるものや、軍国主義の復活を想起させるものは、とくに忌避した。担当したのはGHQ=連合軍総司令部の下部機関のCCD=民間検閲支隊で、小林に指示された個所を吉田は一部修正し、原稿用紙に書き写したものの、校正の段階で「全文削除」扱いとなった。「戦闘そのものの記録ではあってもあくまで鎮魂のための挽歌ではないか」と小林は<しかるべき筋>を動かしてCCDの最高責任者の少将に抗議文を出したが回答はなかった。さらに吉田茂の息子で英文学者の健一や小林から頼まれた白洲次郎も動いたが、第二輯にも掲載されることはなかった。
CCDには下読み役として多くの日本人が働いていた。彼らにとって文語体で書かれた吉田の原稿そのものが拒否反応を与えるのではないかという<うがった見方>もあった。吉田健一や白洲たちの働きかけが多少なりとも軟化を誘った側面もあったかもしれないが、万一の場合は出版社自体がつぶれてもかまわないということで、「カストリ雑誌」を手掛けていた銀座出版社を見つけてきた。ためしに『サロン』24年6月号に口語の『小説戦艦大和』を掲載したがCCDからは何の反応もなかったこともあって、それを若干手直しして単行本の『軍艦大和』が計画された。題名を戦艦ではなく軍艦と変えたのもいささかの配慮かもしれない。ところが投書があったのか、CCDは編集長と吉田を呼び出して丸一日も色々と尋問した。その後の折衝で「口語体で、かつ、狙いは鎮魂に徹する」という主張がかろうじて認められたものの、当初は末尾に掲載する計画だった『戦艦大和ノ最期』は割愛せざるを得なくなった。その際に提供されたと思われる米軍撮影の「大和轟沈の瞬間」の航空写真もかなりの遠景からのもので、当然ながら機影はいっさい写っていない。
吉田は高校時代からバッハに傾倒していた。入隊の前夜も日比谷音楽堂でその「無伴奏ソナタ」を聞いた。入場券が売り切れていたが、懇願して入場を許され、観客席の横にある通路の階段に座して最後まで聴き続けた。その印象は強烈だった。
大和の艦影もとっくに消え、機銃掃射の音さえかき消すような負傷者の阿鼻叫喚の声も重油の海からは聞こえなくなった。
望むべくは、時を得てただ死を潔くすることのみ。ひたすらにかくみずからを鞭打つ。
ふと思う。この貴重の時。真の音楽をきくのは今を措いて他にあろうか。
聴こう。心さえ直ければきける。一瞬を得るのだ。
自分の音楽を持たなかったのか。すべては偽りだったのか。
――待て、今きこえてきたもの、たしかにバッハの主題だ。
――違う。作為だ。眩覚じゃないか。
『軍艦大和』からは、あえてこの一章しか紹介しないが、吉田は後年の著作で「バッハの主題」は「無伴奏ソナタ」であったと書いている。記憶のかぎりない純化と深化はさながら至高の叙事詩でもあろうが、偶然生かされるという運命によって負わされた、重すぎる使命を人生に重ねるように吉田は生きた。