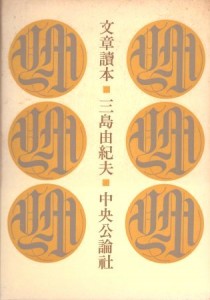書斎の漂着本(70)蚤野久蔵 文章讀本
三島由紀夫『文章讀本』(中央公論社)の外函は三島のイニシャル「Y・M」をあしらった円を六つ並べたデザインである。表紙は鳶(とび)色の和紙に天武天皇も愛した朱華(はねず)色の背布が配してある。<雑文屋>の私にとって名文家諸氏のなかでも三島を取り上げるとなると・・・じゃあ装丁からにするか、ということでこう書き出すことにした。
名文家諸氏というのは丸谷才一『文章読本』(同、昭和54年)の冒頭に「昭和9年、谷崎潤一郎が『文章讀本』をあらはしてのち、同じ題、あるいはよく似た題の本を三人の作家が書いた。昭和25年の川端康成、昭和34年の三島由紀夫、昭和50年の中村真一郎である。そして今またわたしが『文章讀本』なるものに取りかからうとする」から引いた。題名はさておき、終生、「歴史的仮名づかひ」にこだわった丸谷だけに、ここだけは<丸谷流>にしておく。
二番手の川端は同じ題名ではなく『新文章讀本』と「新」を付けた。三番手の三島としては当然、前二作を意識しただろうが、あえて谷崎と同じ『文章讀本』に戻した。冒頭の章で「昨今の『文章讀本』の目的が、素人文学隆盛におもねって、だれでも書ける文章讀本というような傾向に陥る傾きのあるのを、少し苦々しく思うためにほかなりません」として「私はここでこの『文章讀本』の目的を、読む側からの『文章讀本』という点だけに限定した方が、目的も明確になり、素人文学に対する迷いを覚ますことにもなると思うのです」と書き出す。
もともとこの年の雑誌『婦人公論』1月号の別冊付録として出されたのが反響を呼んだため、急遽、同年6月25日に単行本として刊行された。内容は散文と韻文、短編小説と長編小説の文体の違い、戯曲・評論・翻訳の文章、文章技巧などが三島らしい着想と美学で解説されている。その後も中公文庫で重版され続けているから三島自身も想定外のロングセラーではあるまいか。「出来上がった文章は、私のそれぞれの年代、それぞれの時代に考え、感じたことの真実を現わしているので、それを時がたってから修正することは不可能だと考えるからであります。私にとって推敲は、原稿用紙一枚一枚の勝負です。そうして原稿用紙の一枚のなかで文章が行儀よく収まり、一定の密度をもち曖昧な部分がなければ、それで次に進みます」としてこれを書いた時点で三島の思考対象になった内外100人以上の例文を掲げている。当然ながら谷崎の引用は森鷗外に次いで多いし、珍しいところでは山下清の文章まで登場する。
なぜロングセラーとなるのかを考えると「文章読本」とか「文章、論文、作文技術」などという題名が文学愛好家の購入意欲を<そそる>からである。帯にも「万人必読の文章読本!」とある。かくいう私も本棚を見渡しただけで吉行淳之介編『文章読本』、井上ひさし『自家製 文章読本』、向井敏『文章読本』、斎藤美奈子『文章読本さん江』、林真理子『林真理子の文章読本』から始まってコーナーができるほどある。蔵書整理のたびに古書店に引き取ってもらってもこうだから、こうした題名によほど<そそられやすい>性格なのだろう。なかには物理や応用物理などの専門学会で研究発表をする際の平均発表時間がわずか10分で、この制限内に論文をどう紹介するかを書いた山本夏彦の『理科系の文章読本』(文藝春秋『完本 文語文』)というのもある。専門学会など無関係なのに、いやはや。
いささか脱線してしまったが三島の『文章讀本』でおもしろいのは最後の「附 質疑応答」である。「人を陶酔させる文章とはどんなものか」から始まって「造語とは?」までの15項目あり、全部紹介したいぐらいではあるがいくつかを。
「小説第一の美人は誰ですか」
これはごく易しい質問です。文章における小説第一の美人とは、もしあなたが小説を書いて「彼女が古今東西の小説の中に現れた女性のなかで第一の美人であった」と書けば、それが第一の美人になるのです。言語のこのように抽象的性質によって、小説中の美人の本質が規定されます。これが劇や映画と小説との本質的な違いであります。それはまた小説と歴史の違いでもありまして、歴史が史上最高の美女というときには、なんらかの裏付けがなければならないのでありますが、小説はそれ自体によって成り立っている小宇宙でありますから、なんらかの裏付けなしに、小説の第一の美女というものはいつでも任意の所、任意の場所に出現するのであります。しかし私の読んだなかで最も神に近い美女をあげろと云われれば、おそらくリラダンの描いた「ヴェラ」をあげるべきでありましょう。
「方言の文章について」
谷崎潤一郎氏の『細雪』がもし東京弁で書かれたところを想像すれば、方言というものが文学のなかで、どれだけ大きい力をもっているかがおわかりでしょう。『細雪』の翻訳がこのような方言の魅力を伝えなかったら、どれだけ効果を薄くするか想像にあまりあります。谷崎氏は生粋の江戸っ子でありますが、上方に移住してからこの方言の面白さに心を奪われ、さまざまな関西弁の小説を書きました。『卍』は関西弁で書かれた傑作であって、あの不思議な、ぬめぬめとした軟体動物のように動きをやめない小説の構造は、あの独特な関西弁を除外しては考えられません。(中略)しかし方言を駆使するには一つの外国語を修得するくらいの苦労がいるので、その土地に生まれた人間でなければ、本当の方言の味を出すことはできないと言ってもよろしい。谷崎氏は『卍』を書くに当たっては、大阪生まれの助手を使ったと言われますが、私の如きなまけ者は、『潮騒』という小説を書くときは、いったん全部標準語で会話を書き、それをモデルの島出身の人に、全部直してもらったのであります。
「造語とは?」
字引に出ていない言葉のことです。一例が、久米正雄氏は微苦笑という言葉を発明し、今日ではそれは誰でも知っている言葉になりました。これこそ小説家のセンスが、人間のまぎれもない表情をとらえて、そこから新しい作った言葉で表現を与えたわけであります。私はここでは社会評論家が作って、一時流行させる、いわゆる流行語は問題にしません。文学者の造語とは軽薄な流行語とちがって、いままでにある言葉ではどうしても表現できないことを、言葉を曲げても表現しようとする最大の切実さがなければ意味がないのであります。新人の小説などで、やたらに新造語の用いられている小説は、それだけでも誠実味を欠いたものといわなければなりません。
そういえば11月25日は“戦後文壇の鬼才”と言われた三島が東京・市ヶ谷の陸上自衛隊総監部で自決した「憂国忌」である。その11年前のこの『文章讀本』は小説家の裏話まで紹介した三島の茶目っ気が万人と時代に拍手を持って迎えられた理由でもあったろう。いまさらながら、あの衝撃の事件から45年か、とつぶやいてみる。